

目的でつながる
お悩み相談FAQ
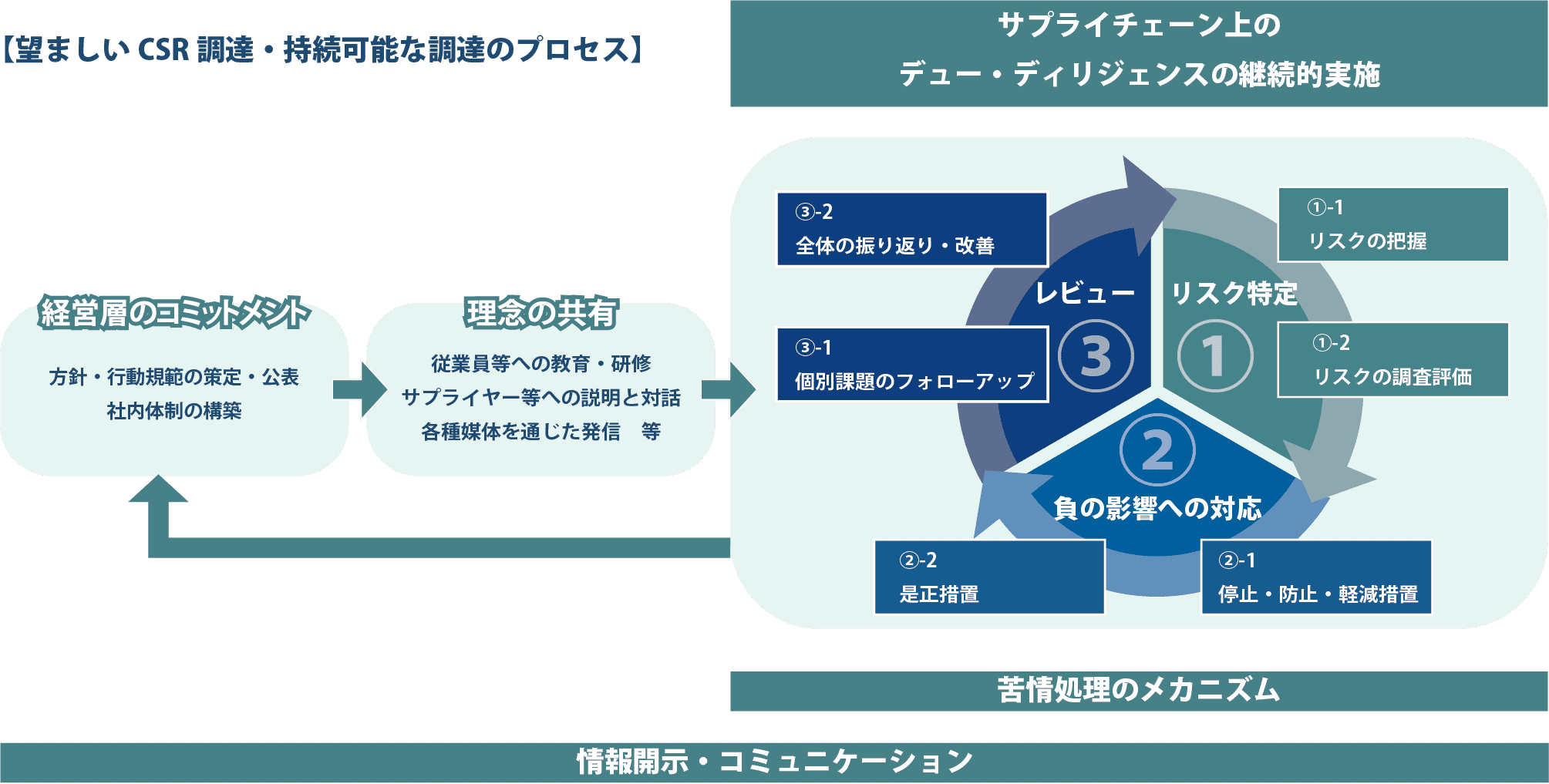
ここではサプライチェーン分科会(以下、SC分科会)お悩み相談ワーキンググループで討議された、CSR調達・持続可能な調達に関する質問と回答をまとめています。CSR調達・持続可能な調達を行う中での疑問や悩みの解決のヒントとしてご活用ください。
なお、ここでの回答は、SC分科会の中でCSR調達・持続可能な調達に携わっている企業の実務担当者の回答の一例であることをご理解ください。
また、より具体的な内容や詳細については、SC分科会内で開催されるお悩み相談ワーキンググループの会員企業間で共有されています。深くお知りになりたい方は是非SC分科会へのご参加をご検討ください。
基本原則の理解
-
A.
GCNJの人権DDマニュアルは「責任ある企業行動のためのOECDデュー・ディリジェンス・ガイダンス」をベースに作成しています。このガイダンスをベースにすることで「OECD多国籍企業行動指針」「ビジネスと人権に関する指導原則」「日弁連:人権デュー・ディリジェンスのためのガイダンス」「経産省:責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」「中小企業のための人権デュー・ディリジェンス・ガイドライン」とも整合します。また、人権DDは人権リスクのPDCA管理であり、この考え方はISOマネジメントとほぼ同じなので、管理手順についてはISOマネジメントシステムの考え方を踏襲しています。つまり、既存のISO(品質、環境、労安)の仕組みに「人権」をそのまま搭載できることを意図しています。
-
A.
SAQはサプライヤーの評価を行うための「調査表」で、人権デュー・ディリジェンスはリスクを管理するための一連の「しくみ」です。人権デュー・ディリジェンスのプロセスの中でサプライヤーのリスク評価を行うためのツールの一つとして、SAQが使われています。
-
A.
例えば以下のような活動が考えられます。
- 役員向け説明会
- CSR部門や調達部門から他部署への説明会
- 顧客からの説明要求があった場合、営業チームと一緒に対応することで、営業チームへのOJT
- グローバル調達チームへの定期的な進捗報告会議
- 本社、工場やグループ企業を回って人権などの説明会やサステナビリティの自分ごと化のワークショップを実施
- 全社員向けE-ラーニング
-
A.
教育訓練に際し、書籍代金や外部のセミナー受講料等がかかることはありますが、それ以外は基本的に交通費等の実費のみということが多いようです。企業によっては、専門家の外部講師を招聘し、年間数回社内やサプライヤー向けに講演会を開くこともあり、その場合はかなりコストがかかるようです。GCNJサイトでは無料のE-ラーニングや教育目的の映像も掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
-
A.
組織の目標等に組み入れられている企業では、多くの方がSDGsやサステナビリティを意識し、以前よりは社員の反応が良く、効果があったと感じられます。
ただ、これは普及施策だけの成果ではなく、顧客からの要求や目標への組み込みなどの影響も大きいと考えられます。
また、社会課題起点でのビジネス創出や、能動的な行動につなげるには今後の浸透が課題です。 -
A.
一般的に社内に専門組織がある企業では、法務やサステナビリティ部門など、主管部門が行うことが多いようですが、調達部門が積極的な企業においては、自ら動き、サステナビリティ部門と連携しているケースもあります。 また、社内のみだと情報量が足りないため、外部有識者やイニシアチブ(GCNJ等)を活用し、社外からも積極的に情報を収集する努力が必要です。
調達方針・行動規範
-
A.
まずは「丁寧な説明をする」「コミュニケーションによって理解を促す」ということではないかと思います。また直ぐに取引を行わないと突き放すのではなく、なぜ断ったのか理由を確認することをお勧めします。
これはガイドラインの内容を細かく精査された上でサプライヤーの方針と相いれない内容がある場合などがあり、何が相いれないのかを確認するのも、サプライヤーとのコミュニケーションの一環として重要なことだと思います。
また、断ってきたサプライヤーと取引を継続する場合は「優先的に監査をする」「監査時に入念に確認する」「監査(調査)頻度を上げる」といったように”重点管理”の扱いにするといった方法もあるでしょう。 -
A.
一般的にはサプライヤー行動規範や根拠となる遵守すべき国際規範が改訂された際に再確認することが多いようです。
一方、毎年、行動規範やSAQを送付する企業もあります。また、取り組みが不十分と思われたサプライヤーにだけ、毎年ポリシーや同意書を配布するという企業もあるようです。 -
A.
各国の法律の詳細については、法務部門と確認しながら対応を進めるのが良いかと思います。
例えば、EUデューディリジェンス指令であれば、人権DDの理解のために経産省から出ているガイドラインやGCNJの人権DDマニュアル等を参考に、少しづつでも人権DDを実施することを推奨します。
また、サプライチェーン分科会のWG活動に参加することで、勉強しながら具体的な対応を進められてはいかがでしょう。 -
A.
調達部門等を巻き込む場合、説明会やオンライン研修などでCSR調達の重要性を理解してもらうところから始めます。そして、CSR調達を自分事として捉えてもらう必要があります。
例えば、座学だけでなく、SAQのフィードバック面談に同席してもらったり、期初の目標設定の際に、サステナビリティに関する目標を調達部の担当者に割り振ってしまうなど、おのずと調達部門の方も意識せざるを得ない状況設定が有効です。粘り強く何度も訴えることや、組織のトップの認識も非常に影響が大きいです。
取引先説明会
-
A.
サプライヤーに対して、個別、又は合同で説明会を開催することが多いようです。その際は、GCNJの各種ツール(「CSR調達入門書」や「CSR調達研修用ツール・セット」)等を利用することもおすすめです。
海外のサプライヤーはYoutubeなどで自社の取り組みについて配信し、その内容を見たうえで、サプライヤーミーティングで要求事項を説明する、などされているところもあります。
SAQ
-
A.
「顧客からの調査・アンケート依頼には100%回答している」という企業も多く存在しています。
一方で、サプライヤーの回答率に関しては、GCNJのCSR調達アンケート(SAQ)で、回収率100%:16.1%, 90%以上: 44.6%, 80%以上: 19.6%の結果*でした。必ずしもすべてのサプライヤーが回答するわけではないようです。*2023年サプライチェーン分科会実施のアンケート結果
-
A.
GCNJのSAQを多くの企業様が使用するようになると、依頼側・回答側の両方で効率的な運用が可能です。今後GCNJとしても、SAQを広く使っていただけるよう、情宣活動を進めます。また、予算がかけられるようであれば有料プラットフォームの利用も有効です。
-
A.
- 購買金額の上位〇%(一般的には90%~70%)のサプライヤーを対象とする
- CSR調達リスクの高い会社(紛争鉱物やパームオイルなどのハイリスク原料、小規模企業などの観点)
- 取引金額+CSRリスクの高い会社の組み合わせ
- 特に定めず、すべてのサプライヤーを対象とする
などの例があります。
-
A.
各社様々ですが、1回/1年~2年程度の企業が7割以上を占めるようです。また、一律ではなく、取り組みが不十分と思われるサプライヤーは頻度を増やすといった優先順位付けをする企業もあるようです。
-
A.
社内の共通認識を得るためにも、またサステナビリティ評価でも目標設定をしているかを問われることがありますので、目標値は設定しておいた方が望ましいと考えます。調査対象とするサプライヤーの数や質問の内容によっては、100%回収できるとは限らないので、現実的な落としどころを踏まえたうえで回収目標を設定するのが良いと思います。
-
A.
一般的には、発生可能性と深刻度を鑑みて、優先順位をつけていくとされておりますが、役務調達に関しても、優先順位として支払金額を用いることは可能と思います。しかし、購入金額が少なくても、その企業様のノウハウや人材教育能力などが重要な役務調達先に関しては重要サプライヤーとして考えることも可能と思います。また、物品調達のサプライヤーと同様、”取引金額は大きくないが、発生可能性と深刻度を鑑みてリスクがあると思われるサプライヤー”も優先順位を上げるべきだと思います。
-
A.
GCNJ サプライチェーン分科会でも、共通SAQや人権DDマニュアル(様式集含む)などの無償ツールをご用意しております。また、サプライチェーン分科会参加企業で使用実績の多い有料のSAQツールとしては、Sedex、Ecovadis等がございます。JEITAなど業界団体によって標準的なSAQツールが公開されている場合もあります。
-
A.
SAQの内容を大項目や各社の重要視する項目から分類し、レーダーチャート表示する企業が多いようです。
また、評価結果に応じてGood pointと改善点、総評等を記載します。条件基準を設定し、用意した定型文をパターン別に記載する仕組みの企業もあります。 -
A.
お礼と今後の改善のお願いの意味を込め、SAQに回答したサプライヤー全社に、メールベースでフィードバックを実施する場合が多いようです。
取引金額・評価点などに応じて優先順位を設定し、一部のサプライヤーに訪問や面談を行うなど手厚くフィードバックを実施するという方法もあります。 -
A.
全取扱品を実施するのが理想ですが、リソースの関係上、直接的な原料からスタートし、その後、間接材等に展開する企業が多いようです。ただし、リスクが高いと考えられるアイテムやサプライヤーがあれば、個別に優先順位を上げて検討することも考えられます。
監査
-
A.
一般的に監査の基準はそれまでに自社が策定している「方針」や「ガイドライン」「マニュアル」等が根拠となります。また、評価に外部評価機関を利用している場合は、自社の監査基準もそれに準じたものになります。
-
A.
監査を受け入れないという場合は、そのサプライヤーの原料の重要性、関係性を考慮しつつ、まずはコミュニケーション、監査ではなく訪問という言葉を使いつつ、少しずつ受け入れてもらえるように検討いただければと思います。
-
A.
監査対象をSAQのスコアのみで選定することはお勧めしません。自社のマテリアリティや取扱品のリスク、地政学的リスク、対象との関係性等総合的に検討して監査対象を選定するべきです。
基本的な考え方として、本来は「すべてのサプライヤーを監査すべき」ですが、現実的なリソースの問題がありますので、状況を総合的に考えて、各社で「形骸化せず効果的に実施できる範囲」で監査を行うのが良いと思います。 -
A.
SAQ回答内容について承知している方は当然ご同席いただくとして、回答内容によっても同席するべき方が異なると思います。事前にどのような議題になるか、また質問をするかを伝えた上で、必要な人選を先方に依頼するのが良いと思います。
その他
-
A.
購入金額をベースに計算すると削減はできません。まずは金額から物量にすることが必要と思います。そのうえで、物量を減少させるか、または原単位を削減する(サプライヤーからの一次データを取得する)等の対応が必要と思います。
ほかの簡易な方法としてはCDPサプライチェーンプログラムに参加し、該当サプライヤーからの排出量割り当てを開示してもらうというやり方があります。この方法であれば、細かい計算は全く必要なく、サプライヤーごとの排出量の情報が得られます。